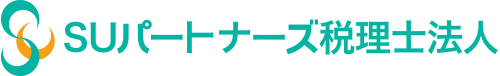国際税務Vol.67 国際的な電子インボイス制度
国際的な電子インボイス制度
国際税務Vol.67
皆様こんにちは。
昨今ITは我々の仕事や生活には欠かせないものとなってきており、会計税務の面でも電子帳簿保存法の施行などデジタルの影響が浸透しつつあります。国際的な潮流も、様々な面でどんどんデジタル化へと向かっています。余談となりますが、デンマークにおいては紙の手紙を出す人が減ったことにより2025年末に郵便配達が廃止されるそうです。時代はどんどん移り変わっていきますね。今回はそのような時代を反映した国際的な電子インボイス制度(e-Invoicing)についての話題となります。
2027年以降、EU加盟国はインボイスのデジタル報告義務制度(Digital Reporting Requirements)を導入し、2035年にはEU共通のe- Invoicingプラットフォームが整備される予定となっています。現在EU内の多くの国が「Peppol」などのXML形式による構造化インボイスを導入しています。アジアにおいてもその波は広がってきており、シンガポールにおいては政府がPeppolをe-invoice標準として採択し、2020年には民間企業にもPeppol対応が義務化されました。
Peppol(Pan European Public Procurement Online)とは、電子請求書などのビジネス文書を標準化・相互交換可能にする国際規格です。文書の仕様・運用ルール・ネットワークについての規格が定められており、認定されたアクセスポイントを通じて異なる業務システム間でも安全かつ機械で読取可能な形で文書交換が行われます。Peppolを採用している国は全世界で35ヵ国を超えました。
日本ではデジタル庁がPeppol Authority(Peppol当局)に指定され、2023年10月のインボイス制度施行にあわせてJP PINTが導入されました。JP PINTとは、Peppolネットワークを通じて請求データの送受信を行うための日本独自の標準仕様です。JP PINTは日本のインボイス制度の要件を満たすため、電子データの統一を目指して策定されました。
JP PINTはPeppolネットワークで電子文書をやり取りする標準規格であるため、海外の企業との請求データ交換もスムーズにできます。2025年1月には、国内企業25社がPeppolネットワークの相互接続テストに成功し、運用実績が拡大中です。
Peppol活用のメリットとしては次のようなものがあります。
・データ入力やチェック作業が大幅に省力化され、生産性が向上します
・人的ミスの削減や仕訳作成の自動化でコストと時間を節約できます。
・海外との請求書交換が標準化され、クロスボーダー取引の効率が改善されます。
一方で、次のような課題もあります。
・既存EDIやPDF、OCRなどを使ったワークフローとの共存により、移行期間中は運用が複雑化する可能性があります。
・日本では電子インボイスの利用はまだ義務化されておらず、取引先が対応していないケースも多く、ネットワーク効果が不十分だと先行投資のリスクもあります。
新たなものを導入する際は、どうしても慎重にならざるを得ません。現時点において、全ての日本企業が導入すべきか、というとそれは微妙なところかもしれません。
ただし、現在の海外の潮流、特にヨーロッパやアジアなどの政府や大企業との取引において義務化または推奨されている状況を鑑みると、海外取引が多い企業は、コストをかけても導入するだけの価値はあるのではないでしょうか。Peppolを導入していること自体が、海外取引先にとっての信頼指標にもなります。特にヨーロッパなどの公共調達分野ではPeppol非対応企業が入札対象外となるケースもあるため、競争力のある取引先と認識されやすくなります。
日本もいつかは郵便配達が廃止され、電子インボイスが全ての企業に対し義務化されるような、デジタル全盛時代が来るのでしょうか・・・?
※この記事は、専門家が掲載時点の法令に基づいて慎重に執筆を行っておりますが、万が一、記事内容に誤りがある、又は、掲載後の税制改正が反映されていないなどにより、読者に損害が生じた場合でも、当法人は一切責任を負いません。
なお、記事に関してご指摘がある場合には、お手数をおかけ致しますが、弊社HP上の「お問い合わせ」のメールにて、掲載記事に関するご指摘等としてお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問には、一切お答えできませんので、予めご了承下さい。