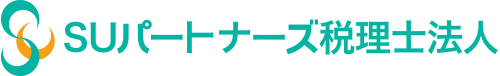相続・事業承継Vol.52 資産管理会社の活用(応用編その3)~個人から法人へ~
資産管理会社の活用(応用編その3)
~個人から法人へ~
相続・事業承継Vol.52
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の宮崎です。
前回のSUレター(相続事業承継Vol.49)で紹介した資産管理会社の活用法の続きです。前回のSUレターでは、個人オーナーの所得を不動産管理会社に移転させるための方法として、最も所得移転ができる方式 不動産所有方式 の留意点を説明しました。今回はその続きになります。
留意点9 借地権の問題をクリアしましょう
土地が個人、建物が法人の場合、借地権の認定課税の問題があります。
<借地権の認定課税とは>
借地借家法により借地人には強い権利があります。反対に、地主には、将来の地代の改訂が困難だったり、借地人からの契約更新の申し出に拒否することが制限されたりします。これらの経済的な不利益を回避するために、権利金を授受することが慣行化されています。
→権利金を授受しない場合、贈与とみなされ「権利金の認定課税」が行われます
次に、様々なパターンで課税関係がどうなるか見ていきます。
① 権利金授受なし
② 権利金授受あり
③ 相当の地代方式
④ 無償返還方式
⑤ 使用貸借
<パターン別課税関係>
①権利金授受なし
権利金の授受がない場合、原則として、権利金の認定課税が行われます。
|
借地人(不動産管理会社) |
地主(個人) |
|
|
借地権設定時 |
権利金相当額※の贈与を受けたものとして受贈益計上 |
課税なし |
|
地代とその取扱い |
通常の地代 損金の額に算入 |
通常の地代 不動産所得の収入金額に算入 |
|
土地の相続税評価額 |
(株価評価) 自用地評価額×借地権割合 |
自用地評価額×(1-借地権割合) |
※権利金相当額=土地の通常の取引価額×借地権割合
借地権割合は、国税庁発表の路線価図に掲載されています。
メリット
・土地が底地の評価となり、相続税評価額が大きく減少する
・受贈益を上回る多額の繰越欠損金がある場合、借地権を無償で移転できる
デメリット
・受贈益が課税対象となる
・借地権の贈与により、法人の株式価値が上昇した場合、地主から法人株主へのみなし贈与課税の可能性がある(相基通9-2)
次に、貸主及び借主が、個人と法人の複数パターンでの課税関係を見ていきます。
|
賃借当事者 |
貸 借 の 事 例 と 課 税 上 の 取 扱 |
|
|
貸主 |
借主 |
|
|
個人 |
個人 |
(事例)父所有の土地に子が建物を建築 |
|
(取扱)借地権を無償で取得したものとして子に贈与税が課税されるが、使用貸借により課税関係なし |
||
|
(注)貸主である父に対する課税関係は生じない |
||
|
個人 |
法人 |
(事例)社長所有の土地に同族法人が建物を建築 |
|
(取扱)法人は借地権を無償で取得したものとして当該法人に借地権の価額に相当する受贈益の認定課税がおこなわれる |
||
|
(借)借地権×××(貸)受贈益××× |
||
|
(注)貸主である個人に対する課税関係は生じない |
||
|
法人 |
個人 |
(事例)同族法人所有の土地に社長が建物を建築 |
|
(取扱)法人は借地権を無償で譲渡したものとして土地の価額のうち借地権部分に相当する価額に対応する部分について土地の譲渡益課税が行われ、また、社長に対する臨時の利益の供与であるため、権利金相当額の賞与の支給があったものとされる. |
||
|
(注)法人税法上、役員賞与は損金不算入 |
||
|
(借)賞与×××(貸)土 地×××(帳簿価額の-部損金算入) |
||
|
譲渡益××× |
||
|
社長は、賞与の支給を受けたものとして給与所得の課税 |
||
|
法人 |
法人 |
(事例)親会社所有の土地に子会社が建物を建築 |
|
(取扱)親会社は借地権を無償で譲渡したものとして土地の価額のうち借地権部分に相当する価額に対応する部分について土地の譲渡益課税が行われ、また、子会社に対する利益の供与であるため、権利金相当額の寄付金の支給があったものとされる。 |
||
|
(注)法人税法上、寄付金は-定限度額を超える部分は損金不算入 |
||
|
(借)寄付金×××(貸)土 地×××(帳簿価額の一部損金算入) |
||
|
譲渡益××× |
||
|
子会社には借地権の価額に相当する受贈益の認定課税 (100%グループ内であれば寄付金及び受贈益の課税なし) |
||
このように、貸主・借主が個人の場合、法人の場合では、それぞれ違った課税関係となり非常に複雑です。
②以降の課税関係については次回以降のSUレターで解説致します。
※この記事は、専門家が掲載時点の法令に基づいて慎重に執筆を行っておりますが、万が一、記事内容に誤りがある、又は、掲載後の税制改正が反映されていないなどにより、読者に損害が生じた場合でも、当法人は一切責任を負いません。
なお、記事に関してご指摘がある場合には、お手数をおかけ致しますが、弊社HP上の「お問い合わせ」のメールにて、掲載記事に関するご指摘等としてお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問には、一切お答えできませんので、予めご了承下さい。