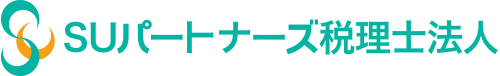相続・事業承継Vol.65 相続直前の相続対策は慎重に!
相続直前の相続対策は慎重に!
相続・事業承継Vol.65
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の宮崎です。
今回は、相続対策における税務リスクに関する重要な事例を取り上げ、皆様にご注意いただきたい点についてお伝えします。
令和6年3月25日に、金沢国税不服審判所において、事業年度変更を伴う株式評価の軽減に関する判決が下されました。この事案では、相続直前に事業年度を変更し、配当金を支払うことで株価を引き下げ、相続財産の評価額を軽減させようとした対策が取られました。これにより、株式評価額は大幅に軽減され、最終的に税額は約50%も減少することとなったのです。しかし、この対策が租税負担の軽減を意図したものであるとして、総則6項に基づき評価額が否認され、最終的には当初の評価額の約2倍の時価純資産価額で課税されることとなりました。
対策前の状況:
本件会社は、相続税評価上、類似業種比準方式と純資産価額方式を併用する方式で評価できる「中会社」に該当していました。しかし、無配当の会社や赤字が継続している会社は、この方式を採用することができず、純資産価額方式で評価することになります。
税法用語としては、「比準要素数1の会社」と定義され、直前期末に配当金額、利益金額、純資産価額(簿価)のいずれか2つがゼロで、かつ、直前々期末にいずれか2つ以上がゼロの会社に該当しますと、純資産価額方式が適用されます。
本件会社は、「比準要素数1の会社」に該当し、純資産価額方式で評価する状況にいました。
事業年度変更と配当金支払い:
一般的に、純資産価額方式より類似業種比準方式の方が評価が低くなる傾向にあります。そのため、「比準要素数1の会社」に該当しないように、配当を支払うという対策は、よく行われています。
ただ、今回の事例では、相続前に事業年度を変更し、配当金を支払う対策が行われています。これは、相続が間近と判断し、次の決算期まで待てないため、臨時株主総会決議に基づき、決算期変更が行われたと推測されます。
税務署の判断:
その後、税務調査において、株主総会の議事録作成に不明点があり、記録が不十分であったことが問題視されました。特に、臨時株主総会の議事録がバックデートされていた可能性があり、税務調査の結果、相続税対策が否認されました。
審判所の判断:
税務調査に納得できない納税者は、不服審判所に申立をしました。
審判所は、これらの行為が租税負担を著しく軽減する結果をもたらしたと判断し、総則6項を適用することが合理的であるとしました。総則6項には、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」 と規定されています。相続税評価は、各通達で規定されていますが、行き過ぎた節税対策には伝家の宝刀で課税するという規定になります。かなり曖昧な規定ですが、この規定があることは注意が必要になります。
リスクを避けるために:
この事例が示すように、相続税対策を講じる際には、適切な書類の整備と手続きが非常に重要です。特に、事業年度変更や配当金支払いによる評価額変更の際には、株主総会の議事録やその他の関連書類を正確に作成し、税務調査に備えることが必要です。
税務署から否認されるリスクを避けるためにも、税理士との連携を密にし、対策を講じる前にしっかりとした準備を整えましょう。特に、相続発生直前の急激な変更には慎重な対応が求められます。
※この記事は、専門家が掲載時点の法令に基づいて慎重に執筆を行っておりますが、万が一、記事内容に誤りがある、又は、掲載後の税制改正が反映されていないなどにより、読者に損害が生じた場合でも、当法人は一切責任を負いません。
なお、記事に関してご指摘がある場合には、お手数をおかけ致しますが、弊社HP上の「お問い合わせ」のメールにて、掲載記事に関するご指摘等としてお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問には、一切お答えできませんので、予めご了承下さい。