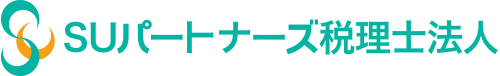相続・事業承継Vol.66 相続税調査にAIを本格導入
相続税調査にAIを本格導入
相続・事業承継Vol.66
こんにちは。SUパートナーズ税理士法人の宮崎です。
いよいよ税務調査もAIの時代に入りました。
国税庁は、令和7年(2025年)7月から、全国の相続税の税務調査において、人工知能(AI)を活用した新たな取り組みを本格的に開始しました。この「AI税務調査」は、AIの高度な分析機能を用いて、申告漏れや過少申告など、税務上のリスクが高いと見込まれる事案を効率的に抽出し、より深度ある調査を行うためのものです。
具体的には、全国の税務署に提出されたすべての相続税申告書をAIによる評価の対象とし、申告書ごとに税務リスクの高低をスコア化します。スコアは0から1までの間で設定され、非常に細かな単位(例:0.01以下)で評価されます。このスコアに基づき、調査の必要性や優先順位を判断することで、限られた調査リソースを最も効果的に活用できるようにします。
今回のAI税務調査は、令和5年以降に発生した相続に関する相続税申告書が対象となります。国税庁ではすでに、全国の税務署から提出された申告データの集約と分析を進めており、調査精度の向上に向けた準備が進んでいます。相続税の申告件数が増加している中で、税務調査の必要性が高い事案も増加しており、調査対象の選定においてAIの活用が期待されています。
AIの導入によって、調査選定の過程は次のように進むようです。
- 全国の税務署から提出された相続税申告書データを国税庁が一括して収集します。
- 次に、それぞれの申告書について、過去の調査結果などを踏まえて、申告漏れなどの可能性をAIが判定し、税務リスクに応じてスコア付けを行います。スコアは、0.01未満の単位で細かく設定され、リスクの度合いをより精緻に把握できるようになっています。
- スコア付けされた申告書データは、再び所轄の国税局や税務署に戻されます。
- 各税務署等の現場では、このスコアを参考に、実地調査を実施するか、あるいは電話などによる簡易な接触で済ませるかなどの対応方針を決定します。
このように、調査の手法も事案ごとに柔軟に選択できるようになっており、より効率的な運用が期待されています。
なお、スコアが0に近く、AIが税務リスクが極めて低いと判断した申告書については、税務調査の対象外とする場合もあります。これにより、調査のリソースを本当に必要な事案に集中させることが可能となり、結果として税務調査全体の効率化が進むと見られています。
では、AIはどのようにして税務リスクを判定しているのでしょうか。その仕組みとしては、過去の税務調査で実際に申告漏れ等が確認された事案や、財産債務調書、その他の法定調書から得られた情報を活用し、申告誤りが生じやすいパターンや傾向を分析しています。その分析結果を基に、全国から集められた申告書データを比較・検証し、それぞれのリスクをスコアとして数値化します。
このように、AIが導き出すスコアは過去のデータに裏打ちされたものであり、単なる予測や推測ではありません。むしろ、法的根拠のある情報に基づいた分析であるため、より信頼性の高いリスク判定が可能となっています。また、AIの分析能力は今後さらに進化していくと考えられており、相続税調査における調査精度や公正性の向上が一層期待されています。
SUパートナーズ税理士法人は、様々なリスクに対し十分な注意を払い、お客様が安心できる相続税申告書作成に努めています。
(参考文献:税務通信3848号 相続税のAI税務調査が7月より全国で開始)
※この記事は、専門家が掲載時点の法令に基づいて慎重に執筆を行っておりますが、万が一、記事内容に誤りがある、又は、掲載後の税制改正が反映されていないなどにより、読者に損害が生じた場合でも、当法人は一切責任を負いません。
なお、記事に関してご指摘がある場合には、お手数をおかけ致しますが、弊社HP上の「お問い合わせ」のメールにて、掲載記事に関するご指摘等としてお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問には、一切お答えできませんので、予めご了承下さい。