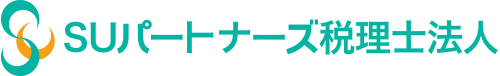相続・事業承継Vol.67 相続財産と遺留分制度について
相続財産と遺留分制度について
相続・事業承継Vol.67
皆さんこんにちは。SUパートナーズ税理士法人の露谷です。
相続が発生した時に相続人の財産はどのように引き継がれるでしょうか?
当然ですがそのまま放置するわけにはいきません。
しかし、いざ財産を分割しようとすると様々な問題も発生してしまいます。
今回はその中でもよく問題となる「相続財産と遺留分」についてお話をさせて頂きたいと思います。
・相続財産ってなんですか?
相続財産とは相続が発生した時、つまり被相続人が死亡した時にその亡くなった方が死亡時に有していた財産(遺産)のことを言います。
財産の種類としては、預金口座にある現預金から建物、土地、有価証券、更には保険金などその相続人が保有していたものはすべて相続財産に含まれます。
そしてこの相続財産を誰が引き継ぐのか?
この相続財産を引き継ぐ権利者(或いは負債者)を確定させる手続きの事を「遺産分割」と言い、相続財産がある場合には避けては通れないものとなっています。
・遺産分割の方法
一般的には被相続人の親族や生前被相続人と親しかった方が引き継ぐことが多く、法定相続人として定められた分を話し合いにより分割したり、あるいは遺言が残されていればその遺言の内容通りに行ったりと、遺産分割にはいくつかの方法がります。
前者、法定相続人として定められた分を話し合いにより分割する場合は、多少のいざこざがあったとしても例外(兄弟姉妹間の仲がとても悪いなど)を除けばおおむね法定相続分(法律で定められた相続人が財産を引き継ぐ事ができる権利)の範疇内での分割が行われることが多いです。
ところが、後者の遺言が残されていた場合はそうはいかない時があります。
それは被相続人が通常とは違う、とても偏った遺言を残してしまった場合です。
・相続財産を誰がどのくらい引き継ぐか?
例えば、被相続人の父が亡くなり息子二人が相続人となった場合。
長男は父親と不仲で疎遠に等しい関係でしたが、次男とはとても仲がよく生前に老後のお世話もしてもらい、とても感謝していました。
そんな状況を鑑みて、父親が残した遺言書には「自分の財産はすべて次男に渡す」とその考えを残していたとします。
すると、次男にとっては財産をたくさん引き継げて嬉しいかぎりですが、反対に長男にとっては法定相続分という法律で定められた権利を侵害されてしまい、相続財産を引き継げない事となってしまいます。
他にも遺言により親族や法定相続人には該当しない赤の他人である「第三者」が被相続人の財産の大半を取得するといった内容が記載されてしまう事もあります。
法的に、遺言書はとても強い効力を持っているため基本的には遺言通りに遺産分割を行う可能性が高いです。
これに納得ができない場合、つまり遺産を相続する双方の協議理解がない場合は裁判所でその内容が争われることとなります。
こうなると、相続財産の引き継ぎどころの話ではなくなってしまいますね。
しかし、ここでひとつ法定相続人にとっては強力な味方となる制度が存在します。
それが「遺留分制度」となります。
・遺留分制度とは?
上記の例えの通り次男がすべての財産を相続し、長男はなにも相続できないというのは法定相続人を定めることに意味をなさない事となってしまいます。
そこで、被相続人が有していた相続財産について、その一定の割合の部分につき法定相続人にその相続財産を保障する法律が存在します。
これが遺留分制度です。
これは被相続人が残した相続財産のうち一定の部分までは法定相続人がそれぞれ引き継ぐ事を法的に認める制度となります。
この「遺留分制度」はとても強い権利となっており、本来なら強い効力をもつ遺言書があったとしても、それを上回るほど強力な制度となっています。たとえ裁判で争いがあった場合でもまず遺留分の保障は認められることとなるでしょう。
・遺言書や相続発生のときには注意が必要
前述の長男にとってはこの「遺留分制度」はとても嬉しい話ですが、逆に生前の父親にとっては自分の意志が反映されず、悔しい結果となってしまいます。
この制度があることから、たとえ相続財産についての遺言書で「この人にこれだけの財産を」と記載していたとしても、それが絶対に執行されるというわけではありません。
この辺りは財産を残す側も財産を受け取る側も十分に注意する必要がありますのでぜひご活用いただければと思います。
※この記事は、専門家が掲載時点の法令に基づいて慎重に執筆を行っておりますが、万が一、記事内容に誤りがある、又は、掲載後の税制改正が反映されていないなどにより、読者に損害が生じた場合でも、当法人は一切責任を負いません。
なお、記事に関してご指摘がある場合には、お手数をおかけ致しますが、弊社HP上の「お問い合わせ」のメールにて、掲載記事に関するご指摘等としてお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問には、一切お答えできませんので、予めご了承下さい。